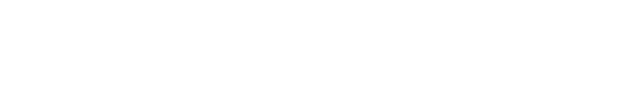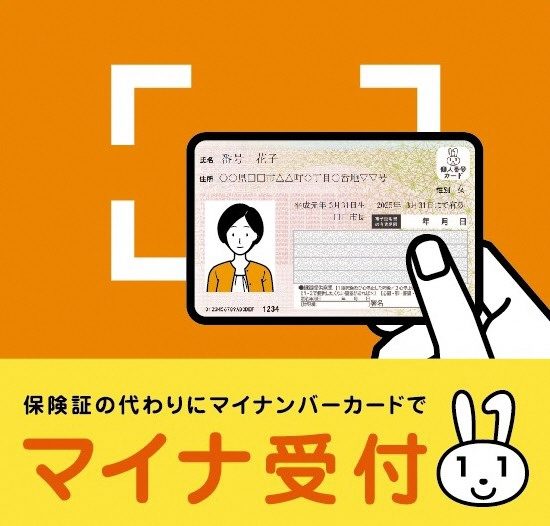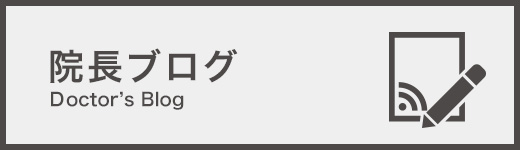「私の平熱は35度なんです」
こういう方が時々いらっしゃいます。日本人の平均体温は36.89度と言われています。そこからするとだいぶ低いです。
過去の報告を見る限り、平熱が35度台の人というのは少数ながら確かにいるようです。しかしこの報告はかなり昔のもので、腋窩温で測定しています。直腸温ならもっと高いのではないでしょうか。
「私の平熱は35度です」という人の多くは、腋窩温が正しく測定できていないのではないかと思います。少なくとも35度前半ということは普通に考えてないでしょう。しかしそのことを指摘しても、平熱35度の人はあまりピンとこないようです。
そしてそのような方が風邪をひいて熱が36.5度だったとする。「平熱ですね」と言うと、「いえ、私の平熱は35度ですからこれは熱です!」とおっしゃるのですが、医療従事者の共通認識として36.5度は平熱だと思います。確かにその方としては上がっているのかもしれませんが、風邪の診断において大事なのは、
平熱もしくは微熱か 高熱か
ぐらいなので、気になるようであれば時々熱を測って観察すればよいだけです。36.5度が平熱か熱かは診断にはほぼ関係しません。
ところで、冷え性が健康に悪いという説は広く流布されており、漢方関係者がこれはビジネスになると思ったのか、「冷え性=万病のもと」として冷え性外来を作ったり、民間療法の人が靴下を重ね履きする健康法を提唱したりと、漢方はまるで冷え性改善のためにあるような風潮すら一部にあるような気がしています。しかし中医学用語に、冷え性に相当するものが思い当たりません。
漢方や中医学の過去を振り返ってみると傷寒や温病など、むしろ熱との戦いが中心で、冷えの治療は主に変症に対するものではなかったかと思います。現代と古代では人間の生活習慣が大いに異なるとはいえ、同じ人間ですから180度違うところまではいかないでしょう。
そして「低体温」=冷え性と思われがちですが、漢方が言うところの「冷え」は体温計のない時代に提唱されたものであり、必ずイコールというわけでもありません。例えば「お腹の冷え」と言いますが、本当にお腹の体温が低いということではありません。
一つ思うのは、腋窩温が低い人というのは体表温度が低い、つまり衣類や空調その他で体温を適切に調節できていない可能性があるかもしれないということです。
更年期によくある冷えのぼせの人は、体が冷えているのに暑がって薄着をしたり冷たいものを食べたりして、さらに冷えのぼせを悪化させてしまいます。寒いと感じるセットポイントが下がってしまうと、知らないうちに体を冷やしているかもしれません。
そのような方におすすめなのは漢方薬ではなく、セットポイントを元に戻す作業、つまり寒さに慣れることと適度な運動をすることです。
現代人は空調の快適な生活に慣れすぎて、暑さにも寒さにも大変弱くなっていると思います。特に室内での生活メインの人はそうです。これは人間の本来の機能が弱まった状態です。
また、いわゆる冷え性は筋力低下で起きることが多いので、筋力をつけることは冷え性の改善になります。
たまにかなりきちんと運動をされ、食事にも気を配っているのに冷え性が治らないという方がいらっしゃるのですが、多分頑張りすぎです。
現代医学が提唱する「健康的な食事」はあっさりした野菜中心のもので、薬膳的には体を冷やす要素が多いと思います。筋トレもやり方によっては便秘したり運動後の体が冷えたりと、冷えにいいことばかりでもありませんし、痩せ型の人が冷え性を改善するにはある程度の脂肪も必要です。ストイックすぎる生活は、大谷選手ぐらいのパワーがあれば何てことないでしょうが、細身の女性にはちょっと厳しいのではないかと思います。何事もほどほどに。そして冷え性はあまり面白いことはせず、生活習慣の見直しで改善するのが良いと思います。
…という当たり前のことを言うと怒り出す患者さんがいるので難しい所です。「そんな当たり前のことを聞きに来たんじゃありません!」いや、その当たり前ができていれば、今ここに来なくてよかったのでは、という気もしますが、このように医師の提案は大体ごくシンプルなものです。