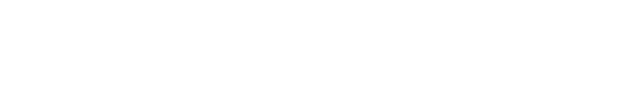認知症のパラダイムシフト
「認知症パラダイムシフト」という本があります。認知症の患者さんは増加傾向にあり、高齢者の5人に1人から、将来的に3人に1人が認知症になると言われています。そして現状では、症状を大幅に改善するような薬がありません。
そのため認知症のケアが非常に大事になります。認知症の患者様ご本人のためならず、我々の安全で平和な暮らしのためにも認知症のケアの充実はとても必要なことです。
副題に「究極のn=1」とあるように、これは医師側の視点、つまりn(データ数)=100000のような大規模臨床試験による治療効果の差を追求するものではなく、「その方にとっての最もよいケア」を模索するもの、つまり、絶対的な正解はないものです。
余談ですが今回のCOVID19パンデミックに際し、n=1の発想が本来は必要な場面においても、感染症の権威と呼ばれる医師達がn=100000(以上)の発想を徹底してしまい、n=1の疑義を呈する人達を「非科学的」と中傷するという事例が多発しました。それを見て日本の医学は思想的に非常に遅れていると思ったのですが、話が逸れるのでこの話はまた別の機会にします。
話を戻すと、この本の目的は、「認知症患者さんの真の尊厳を守ること」です。
認知症は症状が進むにつれて、いわゆる社会性を少しづつ失っていきます。お風呂に1週間入らない、服を着替えない、昼と夜が逆転する、となりの人のご飯をとってしまう、手づかみでものを食べようとするなどといった行動がみられることもあります。
それに対し介護を行う側の人間はとてもまじめで几帳面、きちんとした人であることも多いでしょう。
ゆえに「こうなければならない」という観念がとても強く、そのことがかえって認知症の方のお気持ちを傷つけてしまうこともあるかもしれません。私たちがなぜ認知症の方々の言動にイライラしてしまうのか、それは私たち自身がとらわれている価値観や常識、固定観念の鏡かもしれないと本は伝えます。
実例として、手づかみでご飯を食べることを注意され介護拒否や徘徊がみられていた方に、手づかみでご飯を食べるようにしてもらったことで、問題行動も減りイキイキとしてきたということが紹介されています。手づかみでご飯を食べるなんて…という所にこだわってしまうとそこから先に話が進みません。(ただしこの話を聞いて、この結論に眉をしかめる人もいるだろうなとは思いますが、そこが「絶対の正解が存在しない」ゆえんでもあります。)
この本の著者は介護側に発想の柔軟さを期待しています。場面に応じサポートの仕方を変える方法だけでなく、「これまでの社会性にとらわれず、その方にとっての新しい社会性を構築していく」作業なので非常にクリエイティブで、これを楽しいと感じる人も多くいるのではないかと思います。
認知症の方のご家族としては、「あんなにきちんとしていた母(父)が、こんなにいい加減な人になってしまうなんて」というショックが大きいことは容易に想像できます。ご家族自身の加齢に対する不安と重なってしまうこともあるでしょう。
そのことが認知症の方に対する叱責や行動の抑制につながり、結果、日々の暮らしの自由さを奪ってしまっているということも、もしかしてあるかもしれません。
認知症の介護で私たち家族はつい、「本来の母らしさ、父らしさ」を取り返したいと考えてしまうかもしれませんが、本はこのように伝えます。
「人はもともと多様な顔を持っており、家族にも見せていなかった顔が、認知症になって出てくることもあります。それも含めすべてが本人であることは疑いようがない事実です。要は、プロの介護者も家族も、認知症を有する方の『その人らしさ』を決めることはできない、そんなことは誰にもできないのではないか、いわば『その人らしさ』というのはあってないようなもの、ほとんど幻想と言っていいかもしれません。であるならば、その方の過去を取り戻すよりも、今のあるがままのご本人を受け止めた中で、いかに穏やかに過ごしていただくことができるか、そこがケアの主眼になる所です」
この本を読んで、私はAIはまだこのケアの主眼に考えが至る所までにはならず、認知症のケアに関しては人間にとって代わるものではないと思ったのですが、将来人間に介護されたいか、機械に介護されたいかというのは、私が高齢者になる頃には現実的な選択肢として現れるものかもしれません。