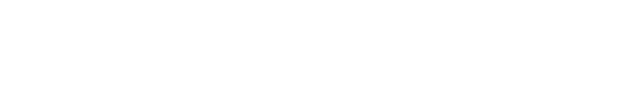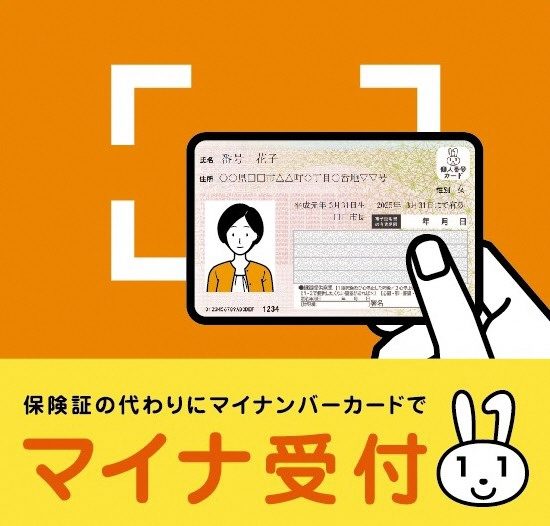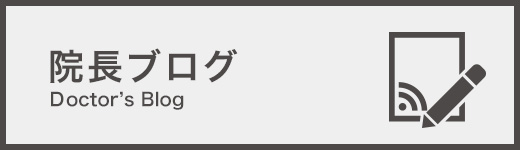不動明王と糖尿病
医療従事者間の共通認識として特定の病気の患者さんのステレオタイプというのはある程度あります。
糖尿病の患者さんのステレオタイプというのは、怒らず聞いていただきたいのですが、「言うことを聞かない人が多い」です。もちろん、とても真面目な方も多いですし、むしろ多くはきちんとコントロールできている方なのですが、どうしても一部のそうでない人が目立ってしまいます。
「糖尿病が悪いと説明してもなんか人ごとみたいな態度」
「人の話を聞いているのか聞いていないのか、理解できているかもわからない」
ということで、当然の如く医療従事者側との信頼関係は結構崩れています。
そしてそういう不良少年、ではなくコントロールの悪い糖尿病患者さんがすぐに病気になるかというと、意外に何も起こりません。総合病院だと医師の交代も多く、数年で他の病院に移ったりしますが、その数年の任期中には多分何も起こりません。そうなると患者さん側も「別に真面目にやらなくても大丈夫じゃん」「糖尿病の数値が悪いとか言って、医者や製薬会社が儲けるためにそうい言っているだけじゃないの」ということになり、ますます話を聞かなくなります。もしかしてこの時点で病院に来なくなくなる人もいるかもしれません。
糖尿病の患者さんのコントロールが悪くなるタイミングが年に何度かある気がしています。主に秋と年明けで、人によっては夏です。秋は果物がたくさんあるから、正月はお餅やご馳走があるからつい食べてしまう、ということです。夏は熱中症予防のスポーツドリンクやアイスでも血糖が上がる人が時々います。
たまに、急激にコントロールが悪くなる人がいて話を聞くと、毎日アイスを2個ずつ食べていたとか、果物を好きなだけ食べていたとか、それは悪くなるだろうという話が出てきます。糖尿病なのはわかっているけど、家族はみんな美味しそうに食べているし、アイスは別に悪いものには見えないし、つい食べてしまう気持ちはよくわかります。しかしお医者さん側からすればこれは「どうしてわかりきったことをわざわざやるのか」ということになります。こういう医者患者間の小さな齟齬が積み重なって、最初に出てきたステレオタイプが形成されてしまうというわけです。
こういう糖尿病のコントロール不良問題は患者さんの不摂生のせいにされがちですが、そうせずに医師側の問題でもあるとしてまともに向き合ったのが石井均先生です。「病を引き受けられない人々のケア」という本は対談形式でわかりやすいです。
糖尿病の食事療法の難しさは、やはり日々の食事を節制しなければいけないということです。しかもそれが原則一生続きます。終わりがないということは努力する気持ちを大いに挫くものです。しかもその食事療法の結果が目に見えて出てくるのはたとえば20年先かもしれず、その頃自分がどうなっているのかは誰にもわかりません。
(もし順調に年を取っていたとすれば加齢も加わって色々体の不調が出ている頃です。糖尿病のコントロールがきちんとできているかがより重要となりますが、その時に慌てて何とかしようとしても遅いのでやはり若い頃からのコントロールが重要となります。それはわかっているんだけど、という話です。)
食事を制限されるということはなかなかのプレッシャーです。自分の経験で話すと、私は子供の頃プリンアラモードが大好物でした。ある日、あまりに肉付きが良い子供になり「もう食うな」と父にプリンアラモードを取られてしまった時のことは未だに覚えています。恐るべし食い物の恨み。
患者さんはさすがにここまでの恨みにはならないかもしれませんが、それでも、医者にかかるたびに「食うな」と言われているような気がしてしまうかもしれません。昔、林真理子氏がエッセイで書いていた氏の若い頃の話を思い出します。カツ丼を食べていた林氏に向かって同級生の男子が「そんなもん食っているから太るんだよ」みたいなことを言ったというもので、その時の林氏のみじめさが身につまされるような場面でした。食事の習慣はプライベートな領域のもので、そもそも他人にあまり介入されたくないですし、正しいとか間違っているとかもあまり言われたくないものでしょう。食事には個人の嗜好以外にも経済状況や生活習慣そのものが反映されるものです。
糖尿病の食事制限というのは本当に難しく、緩くなってしまうこともあれば、時により極端になってしまうこともあります。一時期流行った厳しい糖質制限などがそれですが、普通はそこまで継続できません。(無理な食事を続けられるということ自体がすでに軽い摂食障害になっているような気すらしてきます。)従って挫折することは何ら不思議ではないのですが、挫折したことでまた劣等感に悩んだり、逆にやけになって不摂生に行ってしまうこともあります。長期戦なのでそういう時もまたあって然るべき。また立ち直れる時を待つしかありません。
私見ですが、糖尿病の食事制限は制限というより「より自分に合った食事にしていく」というものです。今までの食事は自分には合っていなかったのです。今や日本は豊かになり、スーパーやコンビニに行けばいくらでも食べ物が買えて、好きなだけ食べることができます。人間の体の自然状態を考えた時にこの状況はすでに異常です。自分以外の人は何とか糖尿病になっていないというだけで、糖尿病にならなかったとしてもそのうち他の病気になるかもしれません。糖尿病はその食の不自然さを見直すきっかけだったと考えることもできます。「好きなものを奪われた」と考える必要はないのです。
一般的にはインスタント食品やすぐ買えるお弁当、お菓子など、お手軽にできる食事は糖尿病によくないことが多いので、食事により時間もお金もかけることになるかもしれません。食べることが好きな人にとっては、このことはそう悪いことでもない気もします。自炊で質のいいスローフードを作り、元気に過ごしている糖尿病患者さんもいるでしょう。食を見直すことが生活そのものも変えていく可能性がありますし、ひいては糖尿病以外の病気の予防に貢献するかもしれません。
こう考えると、糖尿病の食事療法は、考えに値するテーマを結構含んでいます。血糖コントロールの目的も未来の病気の予防なので目に見えず、自覚症状もありません。つまり、この病気のテーマは実はより形而上的なものだということです。
✳︎病気の概念とは何なのか?私は全く自覚症状がないのに医者に行くと糖尿病が悪いと言われるが別にどこも悪くない。数年通ったが、血液検査の数値以外特に何も変化がない。
✳︎血糖コントロールがいい方が各種合併症のリスクが減るのはわかったが、その上で、食事療法には時間もお金もかかり、今の自分にはそれより人生で優先させたいことがある。血糖をきちんと下げることの自分にとっての価値を判断する材料を医師は十分提供できていない。
✳︎医者は自分が糖尿病だというがこの飽食の時代、おかしいのは運動せず好きに食べても糖尿病にならない人の方だ。
✳︎正しい食事とは何か。私に正しい食事を説く医者だって正しい食事をしているのか。
✳︎将来の病気の予防というが、起きるかどうかわからないものをなぜさも確実に起きるかのように言うのか。
この辺の疑問がクリアできていない所が、患者さんが「人の話を聞かない」につながる可能性があるのですが、これらの疑問には実は明確な解がありません。興味を持って考えるための材料としては好材料なのですが、わかりづらいです。一方で血液検査の数値は非常に分かりやすい。分かりやすいものに頼ってテーマの本質が語られないということが往々にして起こっている気がします。
それにしても、こうした抽象的テーマの語り手として、おばさん先生ではちょっと役不足かな…とも思ったりします。いっそのこと、仏の教えを聞かない衆生を正しい道に導く不動明王の像にアマゾンエコーで語って頂いた方が、私よりは説得力があるのかもしれません。